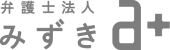フランチャイジーの破産

1 フランチャイザーが破産するとフランチャイズ(FC)契約はどうなる?
以前、フランチャイザー(本部)について破産手続が開始された場合に生じる問題点について触れました。
今回は、フランチャイジー(加盟店)について破産手続きが開始された場合に生じる諸問題について触れます。
加盟店について破産手続が開始された場合、本部にはどのような問題が生じるでしょうか。ロイヤリティや商品・原材料等の代金の未払いがある場合、その扱いはどのようになるのでしょうか。
2 FC契約は継続するか?
多くのフランチャイズ契約の場合、破産解約特約が規定されているのではないかと思います。破産解約特約とは、加盟店について破産手続が開始されたことを契約の解約事由とする旨の特約のことです。
この特約の効力を否定する見解もありますが、有効であるとする見解のほうが有力ではないかと思います(『第3版 フランチャイズ契約の法律相談』349頁、『フランチャイズ契約の実務と書式』219頁など)。
そうすると、この特約がある場合は、本部は、加盟店の破産を理由にFC契約は解約できることになります。
このような特約が規定されていない場合や、特約があっても本部が解約権を行使しない場合には、原則として、加盟店が破産手続を開始しても、それのみを理由にしてFC契約が消滅することはありません。
「フランチャイザーの破産」においても解説したように、破産管財人には、契約を履行して営業を継続するか、契約を解約するかを選択する権利が認められているため(破産法53条)、FC契約が継続するか否かは、破産管財人の選択に従うことになります。
なお、加盟店が破産手続を開始するほどに経済的に逼迫しているのであれば、破産手続の開始以前に、本部への債務不履行(ロイヤリティや、商品・現在料等の代金の未払い等)が生じている場合も多いかと思います。その場合には、破産解約特約がなくとも、加盟店の債務不履行を理由にFC契約を解除することができる可能性が高いです。
3 FC契約を解約した場合
加盟店が破産手続を開始した時点で、本部が加盟店に対して何らかの財産上の請求権を有していた場合には、その請求権は、原則として破産債権として扱われ、本部は、破産債権者として配当を求めることになります。
もっとも、FC契約においては、加盟店から本部へ、(加盟)保証金が差し入れられていることが多いので、未回収の債権については、この保証金と相殺することによって回収することが可能です。
相殺によって未回収の債権が全額回収できた場合に、保証金の残額があれば、本部は破産管財人へ保証金を返還する必要があります。反対に、全額を回収できなかった場合には、未回収分については破産債権として扱われます。
なお、破産法においては、意図的な相殺状態の作出により優先的な債権回収を可能とすることが禁止されています。本来配当を受けられる可能性のある他の債権者が、特定の利害関係人の意図的な相殺によってその権利が害されてしまうことを防止するためです。そのため、加盟店が支払不能状態であることを知って債権を取得した場合などには、その債権を保証金と相殺することはできません。つまり、加盟店が債務超過状態にあり、そのすべての債務を履行することが不可能な状態に陥っていることを知りながら、商品や材料の供給、ノウハウの提供を行い、その対価としてのロイヤリティの請求権を取得したとしても、加盟店が支払不能状態であることを知った以降のロイヤリティは、保証金との相殺が許されない可能性があります。
加盟店の経営状態が悪化していることを知りながらも、「保証金を預かっているから、多少のロイヤリティの不払いがあっても大丈夫だろう」と高をくくっていると、大きな痛手を負ってしまう可能性があります。FC契約の本部にとって、ロイヤリティの回収は契約の主目的ともいえる最重要事項です。これを回収できなくなるリスクを適切に管理するためには、加盟店の経済状況には常に気をつけておく必要があると言えます。
3 FC契約が継続した場合
破産管財人が契約の履行を選択すれば、FC契約は継続し、本部は引き続き、加盟店に対してノウハウや商品・材料の提供を行う義務を負います。そしてこの場合、仮に本部が加盟店に対して未回収の債権を有していたとしても、それを理由に履行を拒むことはできないと解されています。
また、破産管財人は、「営業又は事業の譲渡」を行うことができます(破産法78条2項3号)。加盟店が破産した場合には、その事業の譲渡が進められることがあります。
しかし、FC契約は、本部と加盟店との信頼関係の下で成立する継続的契約であり、どのような譲受人であっても本部がそれを受け入れなければならないというのでは酷に過ぎます。そこで、事業の譲渡を行うに当たっては、本部の承諾が必要となります。本部が承諾しない限り、破産管財人といえども、勝手に事業譲渡を進めることはできません。
とはいえ、本部にとっても、これまで経営を行ってきたFC店舗をそのまま第三者に引き継がせてすぐに営業を開始させられるのであれば、新店舗開店への投資は最低限で済むため、事業譲渡にも経済合理性を見出せる場合もあります。このような場合には、本部が他の加盟希望者への事業譲渡を仲介したり、本部自ら事業を買い取って、直営店舗化したりすることも有効な手段となることが考えられます。
4 競業避止義務・秘密保持義務について
加盟店が破産した場合、加盟店に課せられていた競業禁止義務や秘密保持義務の効力はどうなるでしょうか。
まず、FC契約が存続する限りは、加盟店はこれらの義務を負い続けます。
では、破産管財人がFC契約の解約を選択した場合、又は、本部がFC契約を解除ないし解約した場合はどうでしょうか。
(1)加盟店が法人である場合
加盟店が法人であった場合、破産によって加盟店は解散し、法人格が消滅することになるため、義務を負う主体がなくなることになり、拘束力はなくなります。仮に法人たる加盟店に所属していた代表者や従業員が、競業を開始したり、ノウハウを漏洩したりした場合に、その責任を追及するためには、契約に基づく効力ではなく、民法上の一般法理である不法行為等に基づく責任を追及することになります。
このような事態は、加盟店の破産に限らず起こりうるものですが、加盟店が法人である場合に、競業やノウハウの流出を防ぐため、競業禁止義務や秘密保持義務の効力が及ぶ人的範囲を、法人たる加盟店のみならず、その代表者やその親族、従業員などに拡張させて契約書を規定している例も見られます。
あまりに広範囲の者にまでその効力を及ぼすとなると、その有効性については、個々の判断が必要となるものと考えられますが、本部のリスク回避の策としては、義務を負わせる主体を広げることも有効な手段であると思われます。
(2)加盟店が個人の場合
加盟店は個人の場合には、加盟店の破産によっても加盟店の人格が消滅するわけではないので、契約において定められた期間は、競業や秘密保持の義務が引き続き課せられると考えられます。破産管財人が事業を譲渡して第三者にFC契約上の地位が移った場合も同様です。
6 まとめ
以上述べたように、加盟店について破産手続が開始されると、債権の回収が困難となったり、事業譲渡が行われたりするなど、法的な判断を要する場面に巻き込まれてしまうことになります。また、競業避止義務や秘密保持義務の拘束力の有無やその範囲についての判断は、専門家によっても見解が異なることがありえます。
このように加盟店の破産の際には、破産手続に関する専門知識と手続の進行を見通す専門的な判断が必要となってきます。また、このような場面を想定してあらかじめ契約書を整えておくことで、適切なリスク管理が可能となることもありますので、経済的なリスクは回避したいものの、法律的な判断に疑問や不安をお抱えの本部の方は、お早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
関連記事