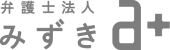解決事例
Solution
事例の概要
後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)
事故態様 歩行者vs自転車
被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。
認定された後遺障害等級
併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。
解決のポイント
近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。
<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。
<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。
自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。