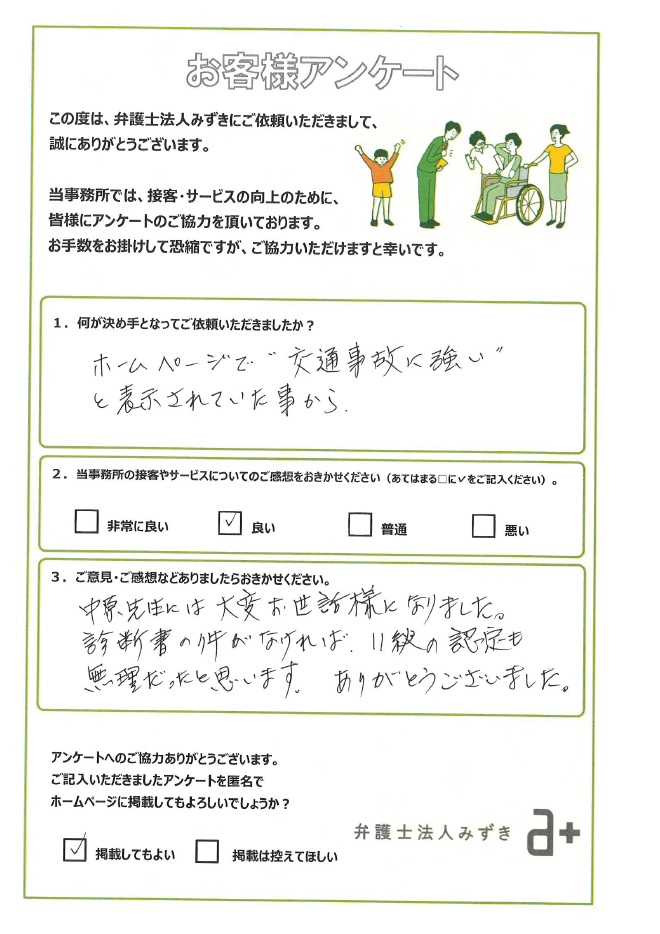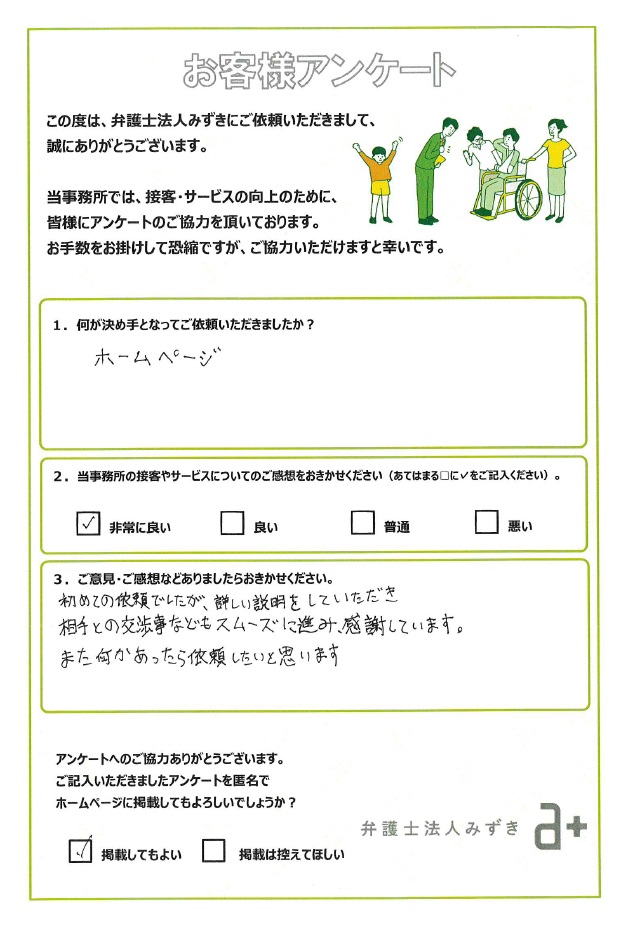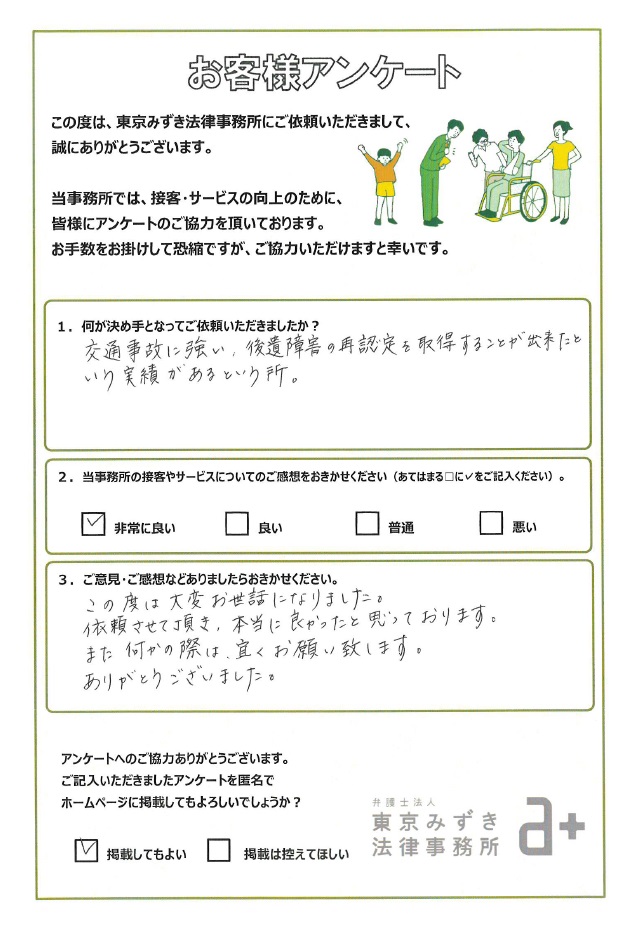【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得

私たちは
交通事故被害者の
""みかたです。
 ご相談
ご相談無料
 多数の
多数の実績
 弁護士
弁護士費用特約
利用可能
 治療中でも
治療中でもご相談可能
交通事故被害者の方、
以下のようなお悩みを
抱えていませんか
-
初めての交通事故でどうしたらいいか分からない
-
「治療費を打ち切る」と言われた
-
治療が長引いていて今後に不安がある
-
後遺障害等級認定を受けたい
-
保険会社から提示された示談金の金額が妥当か分からない
-
相手方の対応に納得がいかない!
交通事故に強い弁護士が
被害者の方を
徹底サポートします。


相談料無料
初期費用0円

平日夜間、
土日祝日の相談可

全国対応
出張相談対応
これまで当事務所は、交通事故被害者の方を対象とした多種多様なサポートに取り組んでまいりました。これまで手がけてきた事件は、交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、重度後遺障害である高次脳機能障害や遷延性意識障害等、死亡事故など多岐にわたります。
交通事故被害に遭うことで人生が大きく変わる方も少なくありません。予期せぬ事故に遭い辛い思いをされた方が将来的にも辛い思いをすることが少しでもなくなるよう、当事務所は誠心誠意サポートします。

交通事故に強い弁護士に
ご相談いただくと
下記の点をお手伝いできます。

事故直後から相手方とのやり取り
当事務所は、事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。「示談金の提示があってから」「後遺障害等級の認定を受けてから」というような制約はありません。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- 交通事故に遭ってしまった
- 保険会社・相手方との対応に不安がある
- この先の進め方を知っておきたい

示談金増額交渉
保険会社が提案してきた示談金は、弁護士が間に入って交渉することによって増額することが多いです。示談を進めてしまう前に、以下のお悩みがある方は是非ご相談ください。
- 保険会社から示談金の提示があった
- 示談金の金額が妥当かわからない
- 示談金の金額に納得がいかない

後遺障害等級認定
当事務所では、 適切な後遺障害等級の獲得に向けて治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までの一貫したサポートを行っています。
- 相手方保険会社から症状固定だといわれた
- 後遺症があるためきちんと賠償を受けたい
- 治療が長引いていて今後が不安
交通事故に強い弁護士が
交通事故被害者を
フルサポート
交通事故解決までの流れ
交通事故問題の解決までには、いくつかのステップがあります。
適切な補償を受けるためには、どのタイミングで次のステップに進むか、それまでに何をしておくかが重要なポイントになります。
警察への通報
まずは警察に通報です。負傷している場合は、救急車も呼ぶ必要があります。
- 加害者側から、きちんと弁償するから警察は呼ばないでほしいと言われることがありますが、警察への通報は、どんな場合であっても行っておくべきです。警察に通報せず、交通事故として処理しない場合、賠償を受けること自体が困難になってしまう可能性があります。
- 事故現場の状況、双方の車両の破損状況は写真を撮っておくと良いです。また、車両をすぐに修理に出してしまうことは控えておいた方がいいです。
物損事故・人身事故
交通事故として警察に届け出た時点では、物損事故(物件事故)として受理されます。もし怪我をしているのであれば、人身事故への切替手続が必要になります。 人身事故に切り替えるためには、警察に病院の診断書を提出し、それを受けて警察が実況見分を行って実況見分調書を作成します。
- 病院で診察を受ける時期は、早いほど良いです。事故から期間が経過していると、事故による怪我であることを証明することが難しくなります。明確にいつまでという期限はありませんが、事故から「1週間あいている」といって保険会社が事故との因果関係を争ってくるケースはあります。
- 実況見分の際は、加害者側の言い分のみで実況見分調書が作られてしまわないように注意する必要があります。実況見分に立ち会い、自分の記憶している事故状況をちゃんと説明しましょう。
- 人身事故と物損事故では、補償の範囲が異なります。人身事故の場合は自賠責の慰謝料を請求することができますが、物損事故は基本的には慰謝料を請求することはできません。物損事故の場合でも、人身事故入手不能理由書があれば物損事故でも治療費、慰謝料、休業損害等を請求することはできますが、裁判になった際の立証責任等、細かいところで人身事故と物損事故とでは違いがあります。
医師の指導にしたがって、定期的に通院をします。医師にあなたの怪我の状況を正確に把握してもらうために、自覚症状は我慢せずにきちんと伝えるようにします。 また、前回の通院と間隔をあけて通院をすると、治療の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。治療の必要があるのであれば、毎月欠かさずに通う必要があります。医師の許可がある場合は、整骨院や接骨院に通うと症状を軽減することもあります。 ただし、この場合にも整骨院や接骨院は医療機関ではないため診断書の作成ができません。医療機関への通院が疎かにならないよう注意しましょう。
- 自覚症状を説明するときは、「手の痺れ」というような簡単な表現ではなく、「肘から薬指にかけての痺れ」というように部位を具体的に限定しておくべきです。
- 治療を続けてもなかなか症状がよくならない時は、治療対象となっている箇所とは別の原因がある可能性があります。その場合は医師によく相談する必要があります。医師が必要に応じて、治療方針の変更することや、専門医にかかってより詳しい検査を受けることを提案してくれることがあります。
- 「治療方針に納得がいかない」、「相性が合わない」ということで転院を繰り返してしまう人もいます。医師との相性もあるかと思います。どうしても折り合いが付かない場合は転院せざるをえませんが、治療方針の決定、検査の実施、後遺障害診断書の作成、この先手続を進めるうえで医師の協力は不可欠です。医師とは良い信頼関係を築くことができるよう心がけるようにしましょう。
ある程度治療期間が経過すると、保険会社から治療費の支払いを打ち切るとの連絡があります。治療費の支払いを打ち切られてしまうと、自費で通院しなければなりません。「完全なもらい事故なのに自分でお金を払って治療をうけなければならないなんて納得がいかない!」という方は多いです。気持ちはわかりますが、だからといって通院そのものを停止するべきではありません。 ここで注意する必要があるのは、保険会社は治療費の前払いの対応を打ち切ると言っているだけであって、この先の治療費を支払わないと言っているわけではないということです。 治療費の前払いが終了(治療費の支払いの打ち切り)した後に被害者が支払った治療費については、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は、裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。 治療費の前払い対応を打ち切られたからもう通院をすることができないと悲観する必要はありません。
- 連絡があるタイミングは事案や保険会社の対応によって異なります。「半年たったけれども治療費の打ち切りの連絡がない」と心配する方がたまにいますが、それ自体には問題はありません。
- 医師の回答や画像データを提出し、治療が必要な状況であるということを説明することによって、治療費の前払いを受ける期間を延長することができる場合があります。
- 自費で通院しなければならなくなった場合、健康保険への切り替えの手続を行うことによって、負担を軽減することができます。交通事故は基本的には自由診療扱いですが、第三者行為による傷病届等を役所に提出することによって健康保険を使うことができるようになります。
治療を継続しても、大幅な改善が見込めず、治療や投薬を行うと一時的に良くなるが、少し経つとまた元に戻ってしまうというように、症状が一進一退を繰り返す状態になることを「症状固定」といいます。 保険会社は、過去の事例を持ちだして、症状固定の時期について判断を迫ってきますが、症状固定の時期をいつにするかは被害者ひとりひとりの症状によって異なります。これ以上の改善が見込めないかどうかを判断できるのは、保険会社ではなく医師です。 交通事故によって負った傷害部分の賠償(入通院慰謝料、治療費、休業損害)は、基本的には事故~症状固定日までとされています。症状固定の時期の判断と、後遺障害認定申請は、交通事故における手続の中でも大事な局面のうちのひとつです。
- 保険会社の担当者の中には、治療費の打ち切りのことを症状固定と話す人もいますが、「症状固定」と「治療費の打ち切り」は同じ意味ではありません。
- 症状固定に至るまでは、多くの傷害の場合、半年から1年程度が目安とされていますが、精神障害のように1年以上を要する傷害もあります。症状固定の時期をいつと判断するかに専門家の意見は不可欠です。
症状固定後に残った症状については、自賠責保険に後遺障害認定申請を行います。後遺障害認定申請の結果、等級が認められた場合は、傷害部分の賠償とは別に、認められた後遺障害に対する「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償を受けることができます。 この後遺障害認定申請をする場合は、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。後遺障害診断書は認定結果を左右する最も大事な書類です。ただ、注意しなければならないのは、医師は治療の専門家であって、交通事故の専門家ではないということです。ほとんどの医師は後遺障害認定診断書の書き方をあまり詳しく把握していません。 なお、後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級より下の等級が認められることや、非該当として後遺障害自体が認められないことがあります。この場合には、異議申立という手続があります。異議申立で、前回の申請の際に不足した資料や医学的所見を補充することによって、認定結果が変更されることがあります。
- 後遺障害診断書作成の際は、適切な等級の認定を受けるため、必要なポイントをおさえて作成する必要があります。
- 傷害によっては、後遺障害認定申請に必要な検査と、治療に必要な検査が一致していないことがあります。どの医師も治療に必要な検査には積極的ですが、不必要な検査に対しては消極的です。適切な等級の認定を受けるためには、該当する検査の数値が自賠法施行令によって定められた基準を満たしていることが要件となります。医師にちゃんと検査に協力してもらうために、必要な検査であることを説明し、理解してもらう必要があります。
ご相談の流れ

お問い合わせ・ご予約
まずはお電話かメールで当事務所までご連絡ください。当事務所のスタッフがご事情やご相談の概要をお伺いします。 お問い合わせの際は、ホームページを見ましたとお伝えいただくとスムーズです。

ご相談
当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いし、見通しやアドバイス、最適な解決方針を提案します。 的確に回答させて頂くためにも、事故時の状況や、その後の経過、怪我の自覚症状など、なるべく詳しくお伝えください。

ご契約
ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、事前に内容をご理解いただいた上で契約書を取り交わすことになります。ご依頼頂いた場合、保険会社との対応や交渉等は、全て当事務所の弁護士があなたに代わって対応することになります。
お気軽にご相談ください
交通事故の被害に遭われた方が気をつけなければならないことは沢山あります。ひとつひとつをご自身で調べながら対応していくのは大変なことです。交通事故被害者の方にとって、弁護士に相談するタイミングに「遅い」はあっても「早い」はありません。是非一度ご連絡ください。
交通事故に強い弁護士が
交通事故被害者を
フルサポート
当事務所が選ばれる理由
交通事故に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、 少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、 当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。

相談料・着手金無料
当事務所は、ご相談無料、着手金無料です。また、各種保険会社の弁護士費用特約にも対応しています。交通事故によって収入が途絶えてしまい金銭的に不安を抱えていらっしゃる方も安心してご相談いただけます。

平日夜間、土日祝日の相談対応
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。 お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。

豊富な解決実績
後遺障害、お怪我に関することは、当事務所が結果に拘り続けている点です。交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、高次脳機能障害や脊髄損傷等の重度後遺障害など、多数の経験を元に交通事故被害者が少しでも良い解決を迎えることができるようサポートします。

各地から利便性の高い立地
後遺障害、お怪我に関することは、当事務所が結果に拘り続けている点です。交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、高次脳機能障害や脊髄損傷等の重度後遺障害など、多数の経験を元に交通事故被害者が少しでも良い解決を迎えることができるようサポートします。

交通事故被害者側を専門対応
当事務所は、交通事故による被害者側の賠償問題を注力する法律事務所として、保険会社側の代理人は行っていません。被害者側特有の問題に対する専門性を追求し、少しでも多くの交通事故被害者の被害回復を図りたいという思いで日々交通事故事件に携わっています。

示談金増額実績多数
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。 お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。
解決事例
当事務所の解決事例の一部をご紹介します。クリックをすると詳細を見ることができます。
「頭部」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)
<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。
コメント
嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。
嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。
交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)
事故態様
バイクvs車
解決に至るまで
この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。
歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。
【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例
後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。
コメント
被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。
通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。
また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。
このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例
後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例(30代 男性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
被害者は横断歩道を横断中、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億0560万円の支払いを受けることで解決に至りました。
コメント
高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。
これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。
さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。4つの能力とは以下の能力を指します。
① 意思疎通能力
記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。
② 問題解決能力
理解力、判断力のことをいいます。
人の支持が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。
③ 作業負荷に対する持続力、持久力
精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。
④ 社会行動能力
協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。
本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。
なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。
後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、同機関の判断に基づき等級が認定されます。
したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療をみまもり、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。
交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。
交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方、是非一度当事務所にご相談ください。
【高次脳機能障害 等】後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例
後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。
被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。
高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。
高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。
これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。
しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。
本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。
交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。
頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。
【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得
事例の概要
後遺障害等級12級13号で保険会社の提示した賠償額から230万円増額して解決(70代 男性)
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、後ろから車に追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。
【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号で230万円増額した事例
事例の概要
後遺障害12級14号、保険会社の提示した示談金の金額から155万円増額(60代 女性)
<事故態様>自転車vs車
被害者は道路を走行中、車両に跳ねられました。
<認定された後遺障害等級>
醜状障害 12級14号
<解決に至るまで>
被害者はこの事故により顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。被害者は、約10ヶ月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。
コメント
醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。
醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。裁判では、裁判所は、醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。
当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。
【醜状障害】後遺障害12級、相手方保険会社の提案額から155万円増額して解決
「肩」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)
事故態様 自転車対車
被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。
なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。
この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。
【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例
事例の概要
保険会社の示談提示額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)
<事故態様>歩行者vs車
被害者が横断歩道をわたっていたところ、右折してきた車に背後からはねられました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形と、その圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。
自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が、裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。
この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり、接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。
【鎖骨骨折】後遺障害12級で賠償額が410万円増額した事例
「上肢」に関する解決事例
事例の概要
併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)
<事故態様>車vs車
被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。
<解決に至るまで>
被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。
休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。
【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定の申請を行い、12級が認定され保険会社の示談提示額から510万円増額して解決に至った事例(60代 女性 パート)
<事故態様>歩行者vs車
被害者は横断歩道を横断中に、左折してきた車にはねられました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、上腕骨近位部骨折、足関節捻挫などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、4ヶ月間の入通院を要しました。被害者が職場に復帰した後、相手方保険会社は被害者に賠償金として110万円の提示をしていましたが、被害者は相手方保険会社の対応に疑問を感じ、当事務所に相談にみえました。被害者に残っている症状が後遺障害に該当すると考えられたため、当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、肩関節の可動域角度の制限により、12級6号の認定がおりました。これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が被害者に提示していた示談額から510万円増額した金額の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例の解決のポイントは、被害者が示談書にサインをする前に弁護士に相談してくれたことだと言っても過言ではありません。
交通事故の被害に遭った方は、事故時の光景やその時の恐怖を何度も思い出してしまいます。早く交通事故の辛い記憶から開放されたい、早く目の前の問題を解決したいという被害者の気持ちに、相手方保険会社はつけこむような対応をしてくることがあります。
この先どう進めたらいいのかわからない、そう思ったら自己判断はせずに、交通事故対応に詳しい弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。
【上腕骨近位部骨折】後遺障害12級で賠償額が510万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)
事故態様 バイクvs車
被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 12級13号
解決に至るまで
被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
コメント
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。
本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。
本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。
非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額
事例の概要
後遺障害認定申請により併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決(50代 男性)
事故態様 バイクvs車
被害者は、バイクで走行中に相手方車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。約9ヶ月にわたり治療を継続しましたが、手首の可動域の制限や、脱臼による肩関節の変形や痛み等の症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま後遺障害として残るのではないかと心配になり、今後の後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については上肢の機能障害で12級6号、肩鎖関節の脱臼については変形障害で12級8号が認められ、最終的に併合11級が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
「TFCC」とは、「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」という手首の小指側付近にある三角形の組織です。手首の衝撃を吸収するクッションの役目を果たしています。TFCC損傷が生じるのは、バイク等で転倒してとっさに手をついた時など、手首に負荷がかかった時です。TFCC損傷の方は、手首を返す、ドアノブを捻るといった動作に困難を生じるようになってしまいます。
TFCC損傷で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、認められる可能性のある後遺障害等級は、生じている可動域制限の程度に応じて12級6号、10級10号、8級6号の各等級が認定されるケースと、痛みをはじめとする神経症状により14級9号、12級13号が認定されるケースの2種類があります。
手首に可動域制限が生じた場合は、その制限の程度によっては、神経症状により後遺障害が認定されるより高い等級が認められることになります。
ただし、後遺障害認定申請で可動域制限が認定されるためには、画像所見上損傷していることがわかる靱帯組織の役割と、受傷後制限が生じている運動の種類とで整合性がとれていることが求められるため、可動域制限が生じていればそれでただちに各等級が認定されるかというとそうではありません。
手首では、「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靱帯組織が多数あり、他の関節と比べて複雑な構造をしています。そのため、後遺障害認定申請の際は、検査結果と画像所見との整合性を証明するために、適切な証拠収集を行う必要があります。弁護士による適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。
本件の場合、被害者はTFCC損傷により手首の関節可動域が健側と比較して3/4以下に制限されていたため、TFCC損傷の部分については12級6号が認定されました。
なお、後遺障害等級は1事故につき1つまでしか認定されないため、今回のように後遺障害12級に該当する障害が2つ残存した場合は、等級がひとつ繰り上がり、併合11級という認定結果になります。
TFCC損傷で適切な等級が認定されるためには、後遺障害認定について適切な知識を有した弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所では、今まで多数のTFCC損傷の案件を取り扱ってきました。その中で培ってきた知識や経験を元に、皆さんが適切な等級の認定を受けることができるよう、全力でサポートします。
是非一度ご相談ください。
【TFCC損傷】併合11級が認定され、2430万円の支払いを受けて解決した事例
事例の概要
異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者がバイクで直進していたところ、左折車両に跳ねられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。
本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。
【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により14級認定。290万円の支払いで解決
事例の概要
異議申立により12級の認定を受け、630万円の支払いで解決(50代 会社員)
事故態様 車vs車
被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた車にぶつけられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害14級が認定されました。この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。
後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。
後遺障害等級認定を受けた方、是非一度当事務所までご相談ください。
【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級獲得。630万円の支払いで解決
事例の概要
後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvsトラック
被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。
また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。
【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得
事例の概要
後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)
<事故態様>バイクvs車
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。
被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい
【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例
「脊柱・体幹」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)
事故態様 同乗者
被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。
複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。
本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。
逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。
【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定
事例の概要
後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例(70代 女性)
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を横断中、相手方車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
8級相当
せき柱に中程度の変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。
解決のポイント
本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。
骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。
交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。
まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。
最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。
二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。
圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。
申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。
三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。
つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。
もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。
例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。
本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。
当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。
【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例
事例の概要
変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例(30代 男性)
事故態様 車vs車
相手車方車両との正面衝突。
認定された後遺障害等級
併合8級
脊柱の変形障害 8級相当(胸椎)
局部に神経症状を残すもの 14級9号(頚椎・胸部)
解決に至るまで
被害者はこの事故により胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。
解決のポイント
後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。
また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。
労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。
本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。
交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。
【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例
事例の概要
後遺障害認定申請により14級が認定された事例(40代 男性)
事故態様 バイクvs車
信号待ちで停車中、後ろから追突される。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 14級9号(胸部)
解決に至るまで
被害者はこの事故により肋骨骨折の怪我を負いました。事故直後から相手方保険会社の対応に疑問を感じており、適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は介入後、相手方保険会社へすぐに弁護士が代理人として依頼をうけた旨の連絡をし、損害の確定のための交渉を進めました。
被害者はこの怪我により7ヶ月間通院治療を行い、骨は癒合しましたが、物を持ち上げる等力を入れた時の胸部痛が残ったため、今後も後遺障害として残存する症状として考えられるとして後遺障害認定申請を行いました。その結果、14級9号が認定を受けたため、認定された結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ね、260万円の支払で解決しました。
解決のポイント
痛みなどの神経症状により後遺障害等級認定を受ける場合、被害者が感じている痛みがどの程度のものかを間接的に判断できる材料を揃える必要があります。判断材料のひとつとしてもっともわかりやすいのは、通院の頻度です。たとえば、ムチウチや捻挫などの怪我を負った場合、痛みを和らげるための治療が必要になることから、通院の回数が少ないと通院が必要ない程度の痛みだったと判断でき、通院の頻度が高いと被害者は治療を必要とする程の痛みを感じていたと判断することができます。ただし、骨折の怪我を負った場合は、通院を多くすることによって骨が癒合するものではないため通院回数自体は少なくなるため注意が必要です。その場合に、どういった資料を提出し、残存する痛みについて説明をつけるかが後遺障害の認定を受けるにあたっての大切なポイントとなります。
この被害者は、骨折部位をギプスで固定することができず、月3回ほど痛み止めを処方してもらう通院治療をしていました。しかし、骨が癒合してきても痛みが消えず、今後の治療をどうするか懸念されていました。そこで、当事務所の弁護士からは痛みが残っている点について後遺障害等級申請も見据えた通院に関する説明を行いました。
骨が癒合した場合でも、骨折の状態、症状の経過、治療経過によって局部に神経症状が残るものとして後遺障害等級が認められることがあります。本件において、当事務所の弁護士は被害者の受傷や治療の状況を精査し、残存した痛みについて説明できる資料を揃えて後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害14級の認定を受けるに至りました。
早くからご依頼いただくことにより、症状や医師の診断を弁護士と確認し、相手保険会社に治療費を支払ってもらいながら将来を見据えた通院治療を受けることができ、結果として症状が残ってしまった場合でも後遺障害等級認定を受けることによって適切な賠償が受けられます。
治療中だからこそ、将来を見据え、この先をどのように進めていくのかを知っておく必要があります。
交通事故による受傷でお悩みの方、まずは一度当事務所までご相談ください。
【肋骨骨折】後遺障害認定申請により14級が認定された事例
事例の概要
併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)
<事故態様>車vs車
被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。
<解決に至るまで>
被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。
休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。
【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例
事例の概要
後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例(60代 女性)
事故態様 歩行者vs車
被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
脊柱の変形障害 11級7号
解決に至るまで
被害者はこの事故により、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をちゃんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は今後後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。
治療7ヶ月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、11級7号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。
事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1ヶ月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。
交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。
例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。
依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。
【胸椎圧迫骨折】後遺障害11級が認められ、800万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。
解決に至るまで
被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。
解決のポイント
相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。
当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。
【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額
事例の概要
後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)
事故態様 自転車対車
被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。
なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。
この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。
【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例
「腰」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害等級14級。当事務所が介入して交渉した結果、400万円増額(50代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで走行中、信号無視の車に衝突されました。
解決に至るまで
被害者は、交通事故により、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。
解決のポイント
相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。
弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。
この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。
当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。
【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級で400万円増額
「下肢」に関する解決事例
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)
解決に至るまで
被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。
素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。
本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。
【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定
事例の概要
後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)
事故態様 歩行者vs自転車
被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。
認定された後遺障害等級
併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。
解決のポイント
近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。
<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。
<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。
自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。
【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
併合第14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例事例(30代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで直進中、相手方車両と衝突、骨折の重傷を負いました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。
解決のポイント
被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。
保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。
保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級で、240万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決(10代 学生)
事故態様 歩行者vs車
被害者は歩行中、車に跳ねられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。
下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。
成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。
お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。
【脛腓骨骨折】後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決
事例の概要
後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)
<事故態様>歩行者vs車
被害者は、歩行中に背後から相手方車両にはねられました。
<解決に至るまで>
被害者は、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8ヶ月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。
解決のポイント
この方は、ご依頼から解決までの期間が1ヶ月弱というスピード解決でした。
相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。
是非一度当事務所までご相談ください。
【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級で、160万円の増額した事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)
事故態様 バイクvsトラック
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。
醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。
【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例
「神経・精神」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、230万円の支払いで解決(30代 会社員)
事故態様 車vs車
被害者はブレーキを踏んだところを後ろから追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部と腰部の慢性的な痛み、頭痛や吐き気等が後遺症として残りました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、230万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
頚椎捻挫・腰椎捻挫は、交通事故による受傷で最も多い傷害です。一般的には「むちうち」と呼ばれることが多いです。むちうちは受傷部位の筋肉や神経に異常が生じることによって症状が生じるため、症状の現れ方は人によって多種多様です。痛みや痺れが主な症状ですが、人によっては頭痛や吐き気、耳鳴りや眩暈が生じる人もいます。
むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような治療を受けたか、どのような検査を受けたか、どのような所見が得られたか等、判断の基準となるポイントが複数あります。治療期間中に資料を収集し、ポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。交通事故によりむちうちとなった人が、受傷が適切に評価されなかったために適切な賠償を受けることができず、事故後の生活で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。交通事故によるむちうちにお悩みの方は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害等級併合14級認定、230万円の支払いで解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例(60代 男性)
事故態様 自転車vsタクシー
被害者は自転車で走行中、曲がろうとした車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。被害者には、本人は事故に遭うまで自覚していませんでしたが、頚椎に椎間板ヘルニアの兆候がありました。被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2ヶ月間の延長する協議がまとまりました。その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8ヶ月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。
こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。
本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。
自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。
後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。160万円の支払いを受けて解決
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。
認定された後遺障害等級
14級9号 局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。
●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。
●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。
本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。
後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級の認定を受けた事例(40代 男性 会社員)
<事故態様>車vs車
被害者は、信号待ちの停車中に、相手方車両に後ろから追突されました。
<解決に至るまで>
被害者は、頚椎捻挫の治療のため、約1年にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残りました。保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあい、事前認定による後遺障害認定申請の準備を相手方保険会社との間で進めていましたが、やはり専門家に申請を頼みたいと当事務所に相談にみえました。当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、適切な賠償額で解決しました。
解決のポイント
この方は、交通事故による怪我の他に既往症があり、交通事故で負った頚椎捻挫が既往症と相まって、より一層辛い神経症状が生じていました。
当事務所で後遺障害認定申請をするにあたって一番注意した点は、現在生じている症状が、交通事故の怪我によるものだとわかるような後遺障害診断書を医師に作成してもらうことでした。診断書等の医療記録を取寄せ、丁寧に治療経過を確認した上で、担当の医師との間で、依頼者の症状が適切に示される等級の認定に関係するポイントをおさえた後遺障害診断書を作成してもらえるよう打合せを行い、申請書類を準備しました。
この方が当初進めていた「事前認定」とは、相手方保険会社を通して行う後遺障害認定申請の方法です。
事前認定により後遺障害認定申請を行った場合、当事務所で行ったような対応を相手方保険会社は行いません。また、後遺障害認定申請にあたって、医師の協力は不可欠ですが、医師もただ後遺障害診断書の作成を依頼されただけでは、どのような点に注意して書類を作成すればいいのか把握していないことがほとんどです。
後遺障害認定申請を行う場合は、後遺障害認定申請に詳しい弁護士に依頼して申請することが適切な後遺障害等級の認定を受ける一番の近道です。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受けた事例
事例の概要
事故態様 車vs車
相手方車両と丁字路にて衝突
認定された後遺障害等級
併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)
解決に至るまで
被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。
本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。
では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。
他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。
もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。
交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。
【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例
事例の概要
後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から270万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)
<事故態様>車vs車
被害者が信号待ちで停車していたところ、後ろから加害車両に追突されました。
<解決に至るまで>
被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年たった頃に、保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあい、まだ痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了しました。その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。
解決のポイント
この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2ヶ月が経過していました。
このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしましたが、もしこれが通院期間が3ヶ月程度だったり、半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみのだった等、通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと、因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。
よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は、裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。
この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。
治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。
【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受け、270万円の増額をした事例
後遺障害認定申請により後遺障害14級9号が認定、260万の支払いで解決した事例(40代 女性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を直進していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等
14級9号
局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。
その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害14級9号の認定を受けました。
認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。
コメント
交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。
この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。
加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。
これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。
しかし、実際はそうではありません。ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。
たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。
そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。
相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。
【頚椎捻挫 等】後遺障害14級9号が認定。260万の支払いで解決した事例
事例の概要
後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から163万円増額して解決に至った事例(60代 男性 会社員)
<事故態様>車vs車
被害者は、車で走行中に加害車両に後ろから追突されました。
<解決に至るまで>
被害者は、病院で頚椎捻挫と腰椎捻挫の治療を受けていましたが、約7ヶ月経過したところで、相手方保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。痛み等の神経症状がまだ残っていたため、後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が提示していた示談額から、163万円増額しました。
解決のポイント
相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。また、この方は休業損害を一部請求していませんでした。休業損害、通院交通費、付添看護費や入院雑費などは、被害者が見落としがちな項目です。中には、請求できることを知らないまま示談に応じてしまうケースもあります。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級で、163万円の増額した事例
「外貌醜状」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)
事故態様 同乗者
被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。
複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。
本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。
逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。
【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)
事故態様 バイクvsトラック
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。
醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。
【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例
事例の概要
後遺障害12級14号、保険会社の提示した示談金の金額から155万円増額(60代 女性)
<事故態様>自転車vs車
被害者は道路を走行中、車両に跳ねられました。
<認定された後遺障害等級>
醜状障害 12級14号
<解決に至るまで>
被害者はこの事故により顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。被害者は、約10ヶ月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。
コメント
醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。
醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。裁判では、裁判所は、醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。
当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。
【醜状障害】後遺障害12級、相手方保険会社の提案額から155万円増額して解決
「むちうち(頸椎・腰椎)」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、280万円の支払いで解決した事例(30代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。
当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。
引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。
本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。
そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。
これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。280万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)
事故態様 車vs車
被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下や頭痛、眩暈、吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決(30代 主婦)
事故態様 車vsトラック
被害者は車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。
医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。
この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。
交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号獲得。260万円の支払いで解決
事例の概要
後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、230万円の支払いで解決(30代 会社員)
事故態様 車vs車
被害者はブレーキを踏んだところを後ろから追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部と腰部の慢性的な痛み、頭痛や吐き気等が後遺症として残りました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、230万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
頚椎捻挫・腰椎捻挫は、交通事故による受傷で最も多い傷害です。一般的には「むちうち」と呼ばれることが多いです。むちうちは受傷部位の筋肉や神経に異常が生じることによって症状が生じるため、症状の現れ方は人によって多種多様です。痛みや痺れが主な症状ですが、人によっては頭痛や吐き気、耳鳴りや眩暈が生じる人もいます。
むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような治療を受けたか、どのような検査を受けたか、どのような所見が得られたか等、判断の基準となるポイントが複数あります。治療期間中に資料を収集し、ポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。交通事故によりむちうちとなった人が、受傷が適切に評価されなかったために適切な賠償を受けることができず、事故後の生活で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。交通事故によるむちうちにお悩みの方は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害等級併合14級認定、230万円の支払いで解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例(60代 男性)
事故態様 自転車vsタクシー
被害者は自転車で走行中、曲がろうとした車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。被害者には、本人は事故に遭うまで自覚していませんでしたが、頚椎に椎間板ヘルニアの兆候がありました。被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2ヶ月間の延長する協議がまとまりました。その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8ヶ月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。
こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。
本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。
自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。
後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。160万円の支払いを受けて解決
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。
認定された後遺障害等級
14級9号 局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。
●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。
●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。
本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。
後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級の認定を受けた事例(40代 男性 会社員)
<事故態様>車vs車
被害者は、信号待ちの停車中に、相手方車両に後ろから追突されました。
<解決に至るまで>
被害者は、頚椎捻挫の治療のため、約1年にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残りました。保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあい、事前認定による後遺障害認定申請の準備を相手方保険会社との間で進めていましたが、やはり専門家に申請を頼みたいと当事務所に相談にみえました。当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、適切な賠償額で解決しました。
解決のポイント
この方は、交通事故による怪我の他に既往症があり、交通事故で負った頚椎捻挫が既往症と相まって、より一層辛い神経症状が生じていました。
当事務所で後遺障害認定申請をするにあたって一番注意した点は、現在生じている症状が、交通事故の怪我によるものだとわかるような後遺障害診断書を医師に作成してもらうことでした。診断書等の医療記録を取寄せ、丁寧に治療経過を確認した上で、担当の医師との間で、依頼者の症状が適切に示される等級の認定に関係するポイントをおさえた後遺障害診断書を作成してもらえるよう打合せを行い、申請書類を準備しました。
この方が当初進めていた「事前認定」とは、相手方保険会社を通して行う後遺障害認定申請の方法です。
事前認定により後遺障害認定申請を行った場合、当事務所で行ったような対応を相手方保険会社は行いません。また、後遺障害認定申請にあたって、医師の協力は不可欠ですが、医師もただ後遺障害診断書の作成を依頼されただけでは、どのような点に注意して書類を作成すればいいのか把握していないことがほとんどです。
後遺障害認定申請を行う場合は、後遺障害認定申請に詳しい弁護士に依頼して申請することが適切な後遺障害等級の認定を受ける一番の近道です。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受けた事例
事例の概要
事故態様 車vs車
相手方車両と丁字路にて衝突
認定された後遺障害等級
併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)
解決に至るまで
被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。
本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。
では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。
他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。
もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。
交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。
【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例
「高次脳機能障害」に関する解決事例
後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。
コメント
被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。
通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。
また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。
このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例
後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例(30代 男性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
被害者は横断歩道を横断中、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億0560万円の支払いを受けることで解決に至りました。
コメント
高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。
これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。
さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。4つの能力とは以下の能力を指します。
① 意思疎通能力
記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。
② 問題解決能力
理解力、判断力のことをいいます。
人の支持が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。
③ 作業負荷に対する持続力、持久力
精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。
④ 社会行動能力
協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。
本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。
なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。
後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、同機関の判断に基づき等級が認定されます。
したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療をみまもり、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。
交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。
交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方、是非一度当事務所にご相談ください。
【高次脳機能障害 等】後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例
後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。
被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。
高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。
高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。
これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。
しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。
本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。
交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。
頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。
【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得
事例の概要
非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。
解決のポイント
高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。
交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。
【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例
「非器質性精神障害」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決(20代 会社員)
事故態様 車vs車
被害者は車で一時停止していたところを相手方車両にぶつけられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、交通事故によりパニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。
非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査期間である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。
本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。
非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。
是非一度、当事務所までご相談ください。
【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号獲得。180万円の支払いで解決
「TFCC損傷」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)
事故態様 バイクvs車
被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 12級13号
解決に至るまで
被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
コメント
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。
本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。
本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。
非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額
事例の概要
後遺障害認定申請により併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決(50代 男性)
事故態様 バイクvs車
被害者は、バイクで走行中に相手方車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。約9ヶ月にわたり治療を継続しましたが、手首の可動域の制限や、脱臼による肩関節の変形や痛み等の症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま後遺障害として残るのではないかと心配になり、今後の後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については上肢の機能障害で12級6号、肩鎖関節の脱臼については変形障害で12級8号が認められ、最終的に併合11級が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
「TFCC」とは、「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」という手首の小指側付近にある三角形の組織です。手首の衝撃を吸収するクッションの役目を果たしています。TFCC損傷が生じるのは、バイク等で転倒してとっさに手をついた時など、手首に負荷がかかった時です。TFCC損傷の方は、手首を返す、ドアノブを捻るといった動作に困難を生じるようになってしまいます。
TFCC損傷で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、認められる可能性のある後遺障害等級は、生じている可動域制限の程度に応じて12級6号、10級10号、8級6号の各等級が認定されるケースと、痛みをはじめとする神経症状により14級9号、12級13号が認定されるケースの2種類があります。
手首に可動域制限が生じた場合は、その制限の程度によっては、神経症状により後遺障害が認定されるより高い等級が認められることになります。
ただし、後遺障害認定申請で可動域制限が認定されるためには、画像所見上損傷していることがわかる靱帯組織の役割と、受傷後制限が生じている運動の種類とで整合性がとれていることが求められるため、可動域制限が生じていればそれでただちに各等級が認定されるかというとそうではありません。
手首では、「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靱帯組織が多数あり、他の関節と比べて複雑な構造をしています。そのため、後遺障害認定申請の際は、検査結果と画像所見との整合性を証明するために、適切な証拠収集を行う必要があります。弁護士による適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。
本件の場合、被害者はTFCC損傷により手首の関節可動域が健側と比較して3/4以下に制限されていたため、TFCC損傷の部分については12級6号が認定されました。
なお、後遺障害等級は1事故につき1つまでしか認定されないため、今回のように後遺障害12級に該当する障害が2つ残存した場合は、等級がひとつ繰り上がり、併合11級という認定結果になります。
TFCC損傷で適切な等級が認定されるためには、後遺障害認定について適切な知識を有した弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所では、今まで多数のTFCC損傷の案件を取り扱ってきました。その中で培ってきた知識や経験を元に、皆さんが適切な等級の認定を受けることができるよう、全力でサポートします。
是非一度ご相談ください。
【TFCC損傷】併合11級が認定され、2430万円の支払いを受けて解決した事例
事例の概要
後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvsトラック
被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。
また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。
【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得
「死亡」に関する解決事例
事例の概要
相手方保険会社が提示していた示談額から650万円増額して解決した事例(80代 無職)
事故態様 車vs車
被害者は友人の車に同乗中、対向車線からきた車に衝突されました。
解決に至るまで
被害者は本件事故により多発骨折等、多数の怪我を負いました。心静止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。
事故発生から2ヶ月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。
ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。
そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。
交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。
具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。
(1) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。
死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。それぞれどのような基準なのかを説明していきます。
まず、自賠責保険の基準についてです。自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。
たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。
次に、裁判所の基準についてです。裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。
裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。
まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。この場合の死亡慰謝料は2500万円です。そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。
(2) 葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。
葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。
そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。
まず、自賠責保険基準です。自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。
次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。
(3) 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。 死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。
死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。
① 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。通常は、30%~50%の範囲となります。年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。
相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。
② 就労可能年数
就労可能年数は原則67歳までです。67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。
このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。
【死亡事故】650万円増額して解決した事例
事例の概要
当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)
事故態様 自転車vs車
被害者は道路を横断中に相手方車両にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。
解決に至るまで
被害者のご遺族は、幼くして亡くなった被害者のためにも、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご遺族の方のお気持ちに応えるべく、相手方保険会社との間で交渉を重ねました。
結果、裁判外の交渉で、裁判所の基準と同様の水準である5500万円の賠償を受けるとの内容で解決に至りました。
解決のポイント
ご遺族は、毎日元気に学校に通っていた幼い我が子が、このような交通事故により突然命を奪われてしまったことに強い憤りと深い悲しみを感じておられました。
ご相談時、親としてお子さんの成長を心から楽しみにしていたと話すご夫婦のお姿には胸が詰まりました。当事務所の弁護士は、そんなご夫婦の姿を目の当たりにし、幼い被害者のため、そしてご夫婦のために出来得る限りを尽くしたいという思いで本件に取り組みました。
本件事故は、目撃者がおらず、加害者が話す事故状況と現場に残った痕跡から推察される事故状況には食い違いがありました。
当初、加害者は事故発生時のことを被害者が原因となっておきた交通事故だと説明していました。しかし、現場に残された痕を調べていくうち、加害者がした説明が事実と相違していることが判明しました。
そこで、当事務所の弁護士は、なるべく真実に近い事故状況を想定し、それをもとに相手方との交渉を重ね、解決に至りました。
交通事故により失われたものが元通りに戻ってくることはありません。
私たち弁護士ができることは、加害者が作り出す加害者に有利な事故状況の主張が事実と相違しているのであれば、他の証拠に基づいてそれに反する事実を主張し、証明し、また、当方の主張に基づいて、相手方保険会社と粘り強く交渉して、ご遺族が適切な賠償を得るためのお手伝いをすることです。
出来ることが限られているという歯がゆさはありますが、弁護士に出来ることを全うすることで、ご遺族の方の悲しみが少しでも和らぐことを心から願っています。
【死亡事故】5500万円の支払いで解決した事例
事例の概要
当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで走行中、前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。
解決に至るまで
被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、相手保険会社が提示する金額が適正な金額なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。
ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。
解決のポイント
本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。
裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。
当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。
交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。
【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1660万増額して解決した事例
事例の概要
当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社の提示額から1300万円の増額した事例(80代 女性)
<事故態様>自転車vs車
被害者は、自転車で道路を横断中に走行中の自動車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。
<解決に至るまで>
相談の結果、相手方保険会社からの示談提案額が、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨を説明し、ご遺族からご依頼を受けました。
示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人、遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。
過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。
結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当所提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。
解決のポイント
保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。
【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1300万円増額した事例
事例の概要
当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例(80代 男性)
事故態様 歩行者vs車
被害者は、歩行中車にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。
解決に至るまで
相手方保険会社からの示談提案額は、入院中の慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益等の各項目で、当事務所が適切だと考えていた額より相当に低い金額でした。
当事務所では、ご遺族からご依頼を受けた後、裁判による解決を図りました。
裁判上で、被害者やご遺族の方のご状況について丁寧な主張立証を行い、当初の示談提案額から1000万円増額した金額で和解に至りました。
解決のポイント
本件で特に争点となったのは、入院中の慰謝料と、死亡慰謝料の金額です。
入院中の慰謝料については、被害者の受傷部位や程度、診療経過等を丁寧に主張立証したことにより、裁判所の基準の2割増の金額が認められました。「裁判所の基準」とはあくまで裁判をした場合どの程度になるのかという基準です。個別具体的な事情によって調整金が加算され、基準より高い金額が裁判所に認められることがあります。
また、死亡慰謝料については、ご遺族の方が事故後心身共につらい状況であったことを主張立証し、裁判所の基準と同等の認定を受けることができました。
交通事故によって失った命を取り戻すことは、残念ながら不可能です。お金が払われたからといって、ご遺族の方の悲しみや喪失感は消えることはありません。せめて、その賠償が適切であったということで、ご遺族の方のお気持ちが和らぐよう、当事務所の弁護士がサポートします。
【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例
「眼」に関する解決事例
「1級」に関する解決事例
「2級」に関する解決事例
「3級」に関する解決事例
後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例(30代 男性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
被害者は横断歩道を横断中、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億0560万円の支払いを受けることで解決に至りました。
コメント
高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。
これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。
さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。4つの能力とは以下の能力を指します。
① 意思疎通能力
記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。
② 問題解決能力
理解力、判断力のことをいいます。
人の支持が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。
③ 作業負荷に対する持続力、持久力
精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。
④ 社会行動能力
協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。
本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。
なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。
後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、同機関の判断に基づき等級が認定されます。
したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療をみまもり、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。
交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。
交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方、是非一度当事務所にご相談ください。
【高次脳機能障害 等】後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例
後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。
被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。
高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。
高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。
これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。
しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。
本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。
交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。
頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。
【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得
「4級」に関する解決事例
「5級」に関する解決事例
「6級」に関する解決事例
後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。
コメント
被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。
通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。
また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。
このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例
事例の概要
非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。
解決のポイント
高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。
交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。
【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例
「7級」に関する解決事例
「8級」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)
事故態様 同乗者
被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。
複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。
本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。
逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。
【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定
事例の概要
後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例(70代 女性)
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を横断中、相手方車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
8級相当
せき柱に中程度の変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。
解決のポイント
本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。
骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。
交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。
まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。
最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。
二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。
圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。
申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。
三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。
つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。
もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。
例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。
本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。
当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。
【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例
事例の概要
変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例(30代 男性)
事故態様 車vs車
相手車方車両との正面衝突。
認定された後遺障害等級
併合8級
脊柱の変形障害 8級相当(胸椎)
局部に神経症状を残すもの 14級9号(頚椎・胸部)
解決に至るまで
被害者はこの事故により胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。
解決のポイント
後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。
また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。
労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。
本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。
交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。
【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例
「9級」に関する解決事例
事例の概要
併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)
<事故態様>車vs車
被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。
<解決に至るまで>
被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。
休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。
【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例
「10級」に関する解決事例
「11級」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決(50代 男性)
事故態様 バイクvs車
被害者は、バイクで走行中に相手方車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。約9ヶ月にわたり治療を継続しましたが、手首の可動域の制限や、脱臼による肩関節の変形や痛み等の症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま後遺障害として残るのではないかと心配になり、今後の後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については上肢の機能障害で12級6号、肩鎖関節の脱臼については変形障害で12級8号が認められ、最終的に併合11級が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
「TFCC」とは、「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」という手首の小指側付近にある三角形の組織です。手首の衝撃を吸収するクッションの役目を果たしています。TFCC損傷が生じるのは、バイク等で転倒してとっさに手をついた時など、手首に負荷がかかった時です。TFCC損傷の方は、手首を返す、ドアノブを捻るといった動作に困難を生じるようになってしまいます。
TFCC損傷で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、認められる可能性のある後遺障害等級は、生じている可動域制限の程度に応じて12級6号、10級10号、8級6号の各等級が認定されるケースと、痛みをはじめとする神経症状により14級9号、12級13号が認定されるケースの2種類があります。
手首に可動域制限が生じた場合は、その制限の程度によっては、神経症状により後遺障害が認定されるより高い等級が認められることになります。
ただし、後遺障害認定申請で可動域制限が認定されるためには、画像所見上損傷していることがわかる靱帯組織の役割と、受傷後制限が生じている運動の種類とで整合性がとれていることが求められるため、可動域制限が生じていればそれでただちに各等級が認定されるかというとそうではありません。
手首では、「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靱帯組織が多数あり、他の関節と比べて複雑な構造をしています。そのため、後遺障害認定申請の際は、検査結果と画像所見との整合性を証明するために、適切な証拠収集を行う必要があります。弁護士による適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。
本件の場合、被害者はTFCC損傷により手首の関節可動域が健側と比較して3/4以下に制限されていたため、TFCC損傷の部分については12級6号が認定されました。
なお、後遺障害等級は1事故につき1つまでしか認定されないため、今回のように後遺障害12級に該当する障害が2つ残存した場合は、等級がひとつ繰り上がり、併合11級という認定結果になります。
TFCC損傷で適切な等級が認定されるためには、後遺障害認定について適切な知識を有した弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所では、今まで多数のTFCC損傷の案件を取り扱ってきました。その中で培ってきた知識や経験を元に、皆さんが適切な等級の認定を受けることができるよう、全力でサポートします。
是非一度ご相談ください。
【TFCC損傷】併合11級が認定され、2430万円の支払いを受けて解決した事例
事例の概要
後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)
事故態様 歩行者vs自転車
被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。
認定された後遺障害等級
併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。
解決のポイント
近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。
<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。
<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。
自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。
【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例(60代 女性)
事故態様 歩行者vs車
被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
脊柱の変形障害 11級7号
解決に至るまで
被害者はこの事故により、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をちゃんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は今後後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。
治療7ヶ月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、11級7号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。
事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1ヶ月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。
交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。
例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。
依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。
【胸椎圧迫骨折】後遺障害11級が認められ、800万円の支払いを受けて解決
「12級」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)
<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。
コメント
嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。
嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。
交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。
【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得
事例の概要
後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)
事故態様 バイクvs車
被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 12級13号
解決に至るまで
被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
コメント
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。
本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。
本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。
非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額
事例の概要
後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvsトラック
被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。
また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。
【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得
事例の概要
当事務所で後遺障害認定の申請を行い、12級が認定され保険会社の示談提示額から510万円増額して解決に至った事例(60代 女性 パート)
<事故態様>歩行者vs車
被害者は横断歩道を横断中に、左折してきた車にはねられました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、上腕骨近位部骨折、足関節捻挫などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、4ヶ月間の入通院を要しました。被害者が職場に復帰した後、相手方保険会社は被害者に賠償金として110万円の提示をしていましたが、被害者は相手方保険会社の対応に疑問を感じ、当事務所に相談にみえました。被害者に残っている症状が後遺障害に該当すると考えられたため、当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、肩関節の可動域角度の制限により、12級6号の認定がおりました。これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が被害者に提示していた示談額から510万円増額した金額の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例の解決のポイントは、被害者が示談書にサインをする前に弁護士に相談してくれたことだと言っても過言ではありません。
交通事故の被害に遭った方は、事故時の光景やその時の恐怖を何度も思い出してしまいます。早く交通事故の辛い記憶から開放されたい、早く目の前の問題を解決したいという被害者の気持ちに、相手方保険会社はつけこむような対応をしてくることがあります。
この先どう進めたらいいのかわからない、そう思ったら自己判断はせずに、交通事故対応に詳しい弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。
【上腕骨近位部骨折】後遺障害12級で賠償額が510万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級12級で保険会社の示談提示額から250万円増額した事例(20代 男性 学生)
事故態様 自転車対車
被害者は、自転車で横断歩道を走行中に、信号無視をした相手方車両にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負い、治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。
逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。
なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。
変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。
この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。
【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級で250万円増額した事例
事例の概要
保険会社の示談提示額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)
<事故態様>歩行者vs車
被害者が横断歩道をわたっていたところ、右折してきた車に背後からはねられました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形と、その圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。
自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が、裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。
この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり、接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。
【鎖骨骨折】後遺障害12級で賠償額が410万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級12級13号で保険会社の提示した賠償額から230万円増額して解決(70代 男性)
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、後ろから車に追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。
【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号で230万円増額した事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)
事故態様 バイクvsトラック
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。
醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。
まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。
次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。
当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。
【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受けた事例
「13級」に関する解決事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)
事故態様
バイクvs車
解決に至るまで
この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。
歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。
【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例
事例の概要
後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決(10代 学生)
事故態様 歩行者vs車
被害者は歩行中、車に跳ねられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。
下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。
成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。
お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。
【脛腓骨骨折】後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決
「14級」に関する解決事例
後遺障害認定申請により後遺障害14級9号が認定、260万の支払いで解決した事例(40代 女性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を直進していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等
14級9号
局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。
その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害14級9号の認定を受けました。
認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。
コメント
交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。
この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。
加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。
これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。
しかし、実際はそうではありません。ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。
たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。
そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。
相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。
【頚椎捻挫 等】後遺障害14級9号が認定。260万の支払いで解決した事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害14級の認定を受けた事例(50代 男性 自営業)
<事故態様>車vs車
高速道路で複数台が絡む玉突き事故です。被害者は前方の車両に乗車していました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷などの怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、3ヶ月間病院に通いましたが、一向に痛みがひかないことから心配し、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、依頼を受けた後、被害者の今までの治療状況を確認し、後遺障害が残る可能性が高いと判断しました。治療の継続を促し、その治療の終了後に当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。これを元に相手方保険会社と交渉し、520万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
痛みには、常時痛む「継続痛」、重たい物を持つ等特定の動作を行った時に痛む「運動痛」等の様々な痛みがあります。
自賠責保険の実務上、後遺障害として等級の認定を受けることができる「痛み」は、常時痛む「継続痛」を指します。したがって、重い物を持った時にのみ痛みがでる場合や、天候が悪い時にのみ感じる痛みは後遺障害等級認定の対象とはなりません。
さらに、自賠責保険から後遺障害として等級の認定を受けるためには、最低限、この継続痛が交通事故による怪我によって生じていることが、医学的に説明できることが必要です。そのためには、通院時に被害者がどのような自覚症状を訴えていたか、各種神経学的検査はどのような所見だったか等の資料収集を行なう必要があります。
交通事故によってむちうちや捻挫を負った場合は、通院期間の資料収集が不十分だったために後遺障害認定申請が非該当だったということにならないために、本事例同様、軽傷だと決めつけたり、そのうち良くなるだろうと楽観視したりせず、事故後しばらくはセルフチェックを十分に行いながら通院を継続し、不安を感じたらすぐに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けた事例
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は、信号待ちの停車中に玉突き事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(首・腰)
解決に至るまで
被害者はこの事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、事故からの治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。その結果、首と腰の各部分で14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。
コメント
交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。
労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。
本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。
交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。
交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。
是非一度、当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害認定申請により併合14級が認定
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)
解決に至るまで
被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。
素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。
本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。
【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定
後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号が認定された事例 (40代 男性 自営業)
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は信号待ちで停車していたところ、後ろからきた相手方車両に追突されました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 14級9号
解決に至るまで
被害者はこの事故により頭部挫傷、頚椎捻挫等の怪我を負い、以降肩の痛み、手足の痺れ等に悩まされるようになりました。3ヶ月治療を続けた段階で、相手方保険会社から、怪我の状態について医師に直接話をききたいとの要望が出ました。被害者は、今後適切な治療を受けることができるのか心配になり、当事務所にご相談にみえ、ご依頼をうけました。当事務所の弁護士は、保険会社と被害者との間に入り、症状固定まで治療を継続できるよう交渉を行い、半年治療した後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫で14級9号の認定を受けました。認定された等級をもとに丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。
解決のポイント
被害者の方と相手方保険会社との間に入ってやり取りしている際によく感じるのが、双方の話の食い違いが多いということです。たとえば、医師が症状固定をいつと判断したかということひとつをとっても、被害者の方からは「年内いっぱいだ」とのお話を伺っていたのを、相手方保険会社からは「11月末」と主張を受ける等です。同じ医師の方から話をきいているにも関わらず、このようなくい違いが生じてしまうことが多々あります。そのような状況になってしまったときに、各所の状況を整理し、スムーズに解決へと進むように調整することも交通事故事案に携わる弁護士の大切な仕事のうちの一つです。
本件の場合、あと少しで治療半年だというところで、相手方保険会社から、医師が症状固定だと話しているというとのことでしたが、医師と被害者の方との間では後遺障害認定申請に備えるためにも、改善を図れる段階まではきちんと治療を継続し、その後で症状固定するとの話しであり、具体的に症状固定であるという話にはなっていませんでした。なぜそんなくい違いが生じたのか状況を確認してみたところ、医師が症状固定の時期、後遺障害診断書を作成について決めかねている部分が一因となっていることが分かりました。当事務所の弁護士は、被害者の方の症状から、治療を継続することについて医師及び相手方保険会社と協議し、治療の継続を図りました。医師の方は後遺障害認定申請の専門家ではもちろんないため、後遺障害認定申請に携わったことがないことや、それが何のための手続なのかを十分に把握していないことも少なくありません。中には、後遺障害診断書について、治療方針に落ち度があったということを記録に残すためのものだと勘違いし、診断書に後遺症が残ったと記録することを極端に身構えてしまう医師もいます。しかし、医師が後遺障害診断書の作成に協力的でなければ、被害者は適切な等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。そうならないためにも、弁護士は後遺障害認定申請について、被害者が適切な賠償を受けるために必要な手続であるということを説明し、理解と協力を働きかけなければなりません。こうして後遺障害認定申請への準備が整っていくのです。交通事故に精通した弁護士がついているということが、被害者はもちろん医師にとっても心強いサポートになるものと思っています。
これから後遺障害認定申請をしたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級が認定された事例
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、280万円の支払いで解決した事例(30代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。
当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。
引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。
本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。
そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。
これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。280万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決した事例(40代 男性)
事故態様 車vs車
被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等の怪我を負いました。約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下や頭痛、眩暈、吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いを受けて解決
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決(30代 主婦)
事故態様 車vsトラック
被害者は車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。
医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。
この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。
交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号獲得。260万円の支払いで解決
「家事従事者(主婦・主夫)」に関する解決事例
事例の概要
事故態様 車vs車
相手方車両と丁字路にて衝突
認定された後遺障害等級
併合14級
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(頚部)
・14級9号 局部に神経症状を残すもの(膝)
解決に至るまで
被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちの怪我を負いました。通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。
交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。
また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。
積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。
注意が必要なのは消極損害です。なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。 なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。
本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。
家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。
では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。
本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。この金額はあくまで最低ラインです。
そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。
他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。
本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。
もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。
交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。
【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例
事例の概要
併合9級の後遺障害で700万円の増額をした事例(50代 女性 主婦)
<事故態様>車vs車
被害者が交差点内を直進中、対向車線から右折車両が出てきて、交差点内で衝突しました。
<解決に至るまで>
被害者は、この事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。
これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。
休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5700円が上限だというような説明をしてくることがあります。
本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9975円となり、日額にするとたった4000円の差があります。この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。
【手関節機能障害、脊柱変形障害】併合9級の後遺障害で700万円増額した事例
事例の概要
後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)
<事故態様>バイクvs車
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。
被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい
【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例
「高齢者」に関する解決事例
後遺障害認定申請により、後遺障害3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)
事例の概要
事故態様 歩行者vs車
横断歩道を歩行中、走行してきた車両にはねられました。
認定された後遺障害等級
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1ヶ月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。
被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。
高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。
高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。
「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害、
「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害、
「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害、
「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害などです。
これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。
しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。
特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。
被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。
発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要がある。高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさはそこにあります。
本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。
ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。
交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。
私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。
頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。
【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級3号を獲得
事例の概要
相手方保険会社が提示していた示談額から650万円増額して解決した事例(80代 無職)
事故態様 車vs車
被害者は友人の車に同乗中、対向車線からきた車に衝突されました。
解決に至るまで
被害者は本件事故により多発骨折等、多数の怪我を負いました。心静止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。
事故発生から2ヶ月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。
ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。
そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。
交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。
具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。
(1) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。
死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。それぞれどのような基準なのかを説明していきます。
まず、自賠責保険の基準についてです。自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。
たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。
次に、裁判所の基準についてです。裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。
裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。
まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。この場合の死亡慰謝料は2500万円です。そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。
(2) 葬儀費用
交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。
葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。
そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。
まず、自賠責保険基準です。自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。
次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。
(3) 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。 死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。
死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。
① 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。通常は、30%~50%の範囲となります。年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。
相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。
② 就労可能年数
就労可能年数は原則67歳までです。67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。
このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。
【死亡事故】650万円増額して解決した事例
事例の概要
当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社の提示額から1300万円の増額した事例(80代 女性)
<事故態様>自転車vs車
被害者は、自転車で道路を横断中に走行中の自動車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。
<解決に至るまで>
相談の結果、相手方保険会社からの示談提案額が、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨を説明し、ご遺族からご依頼を受けました。
示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人、遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。
過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。
結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当所提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。
解決のポイント
保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。
【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1300万円増額した事例
事例の概要
当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例(80代 男性)
事故態様 歩行者vs車
被害者は、歩行中車にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。
解決に至るまで
相手方保険会社からの示談提案額は、入院中の慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益等の各項目で、当事務所が適切だと考えていた額より相当に低い金額でした。
当事務所では、ご遺族からご依頼を受けた後、裁判による解決を図りました。
裁判上で、被害者やご遺族の方のご状況について丁寧な主張立証を行い、当初の示談提案額から1000万円増額した金額で和解に至りました。
解決のポイント
本件で特に争点となったのは、入院中の慰謝料と、死亡慰謝料の金額です。
入院中の慰謝料については、被害者の受傷部位や程度、診療経過等を丁寧に主張立証したことにより、裁判所の基準の2割増の金額が認められました。「裁判所の基準」とはあくまで裁判をした場合どの程度になるのかという基準です。個別具体的な事情によって調整金が加算され、基準より高い金額が裁判所に認められることがあります。
また、死亡慰謝料については、ご遺族の方が事故後心身共につらい状況であったことを主張立証し、裁判所の基準と同等の認定を受けることができました。
交通事故によって失った命を取り戻すことは、残念ながら不可能です。お金が払われたからといって、ご遺族の方の悲しみや喪失感は消えることはありません。せめて、その賠償が適切であったということで、ご遺族の方のお気持ちが和らぐよう、当事務所の弁護士がサポートします。
【死亡事故】相手方保険会社の提示額から1000万円の増額した事例
「未成年」に関する解決事例
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
後遺障害等級第6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は自転車で走行中、相手方車両と衝突しました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、第6級の認定を受けました。
まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。ご両親はお子さんの将来のことを案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
ご両親より、本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。
コメント
被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」より高い金額で、逸失利益については、裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。
通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は「裁判所の基準」となります。裁判所の基準とは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。
しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることはそう容易なことではありません。
しかし、本件では、示談交渉により裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。これは、当事務所の弁護士が、被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について、丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。
また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。
このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。
ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【高次脳機能障害 等】後遺障害6級、6300万円の支払いを受け解決に至った事例
事例の概要
当事務所が主張が理解され、相手方保険会社の提示額から1660万円の増額した事例(30代 男性)
事故態様 自転車vs車
被害者は道路を横断中に相手方車両にはねられ、入院先の病院で事故による受傷のため亡くなりました。
解決に至るまで
被害者のご遺族は、幼くして亡くなった被害者のためにも、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご遺族の方のお気持ちに応えるべく、相手方保険会社との間で交渉を重ねました。
結果、裁判外の交渉で、裁判所の基準と同様の水準である5500万円の賠償を受けるとの内容で解決に至りました。
解決のポイント
ご遺族は、毎日元気に学校に通っていた幼い我が子が、このような交通事故により突然命を奪われてしまったことに強い憤りと深い悲しみを感じておられました。
ご相談時、親としてお子さんの成長を心から楽しみにしていたと話すご夫婦のお姿には胸が詰まりました。当事務所の弁護士は、そんなご夫婦の姿を目の当たりにし、幼い被害者のため、そしてご夫婦のために出来得る限りを尽くしたいという思いで本件に取り組みました。
本件事故は、目撃者がおらず、加害者が話す事故状況と現場に残った痕跡から推察される事故状況には食い違いがありました。
当初、加害者は事故発生時のことを被害者が原因となっておきた交通事故だと説明していました。しかし、現場に残された痕を調べていくうち、加害者がした説明が事実と相違していることが判明しました。
そこで、当事務所の弁護士は、なるべく真実に近い事故状況を想定し、それをもとに相手方との交渉を重ね、解決に至りました。
交通事故により失われたものが元通りに戻ってくることはありません。
私たち弁護士ができることは、加害者が作り出す加害者に有利な事故状況の主張が事実と相違しているのであれば、他の証拠に基づいてそれに反する事実を主張し、証明し、また、当方の主張に基づいて、相手方保険会社と粘り強く交渉して、ご遺族が適切な賠償を得るためのお手伝いをすることです。
出来ることが限られているという歯がゆさはありますが、弁護士に出来ることを全うすることで、ご遺族の方の悲しみが少しでも和らぐことを心から願っています。
【死亡事故】5500万円の支払いで解決した事例
「併合」に関する解決事例
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は、信号待ちの停車中に玉突き事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(首・腰)
解決に至るまで
被害者はこの事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、事故からの治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。その結果、首と腰の各部分で14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。
コメント
交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。
労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。
本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。
交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。
交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。
是非一度、当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害認定申請により併合14級が認定
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)
解決に至るまで
被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。
素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。
本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。
【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定
事例の概要
後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)
事故態様 同乗者
被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。
複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。
本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。
逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。
【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定
後遺障害認定申請により後遺障害14級9号が認定、260万の支払いで解決した事例(40代 女性)
事例の概要
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を直進していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。
認定された後遺障害等
14級9号
局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。
その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害14級9号の認定を受けました。
認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。
コメント
交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。
この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。
加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。
これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。
しかし、実際はそうではありません。ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。
たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。
そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。
相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。
【頚椎捻挫 等】後遺障害14級9号が認定。260万の支払いで解決した事例
事例の概要
後遺障害等級併合14級で、保険会社の示談提示額から320万増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)
<事故態様>バイクvs車
被害者が直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたため、出会い頭に衝突しました。
<解決に至るまで>
この事故で被害者は、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。
被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。
解決のポイント
この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。
被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。
ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。
保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。
この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしてい
【左肘捻挫、左手指捻挫】併合14級の後遺障害で320万円増額した事例
事例の概要
後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決した事例(40代)
事故態様 歩行者vs自転車
被害者は歩道を歩いていたところ、飛び出してきた自転車と接触し転倒しました。
認定された後遺障害等級
併合11級
・第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態でした。被害者の家族は治療のこと、保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。
被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。
当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。
その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。
解決のポイント
近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。
交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。その理由は保険にあります。自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。
<治療費・休業損害>
自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。
他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。
<後遺障害等級認定>
後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。自賠責保険がない場合はこの手続きルートを使えないことになります。
自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。
本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。
自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。自転車による事故で人が亡くなることもあります。
相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。
自転車事故で辛い日々をお過ごしの方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。
【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級相当、1750万円の支払いを受けて解決
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
併合第14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例事例(30代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者はバイクで直進中、相手方車両と衝突、骨折の重傷を負いました。
解決に至るまで
この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。
被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。
解決のポイント
被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。
保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。
保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。
【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級で、240万円の支払いを受けて解決
「休業損害」に関する解決事例
「既往症」に関する解決事例
後遺障害認定申請により併合14級が認定された事例(40代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs自転車
被害者は自転車で走行中、後ろからきた相手方車両と接触しました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(膝・下肢)
解決に至るまで
被害者はこの事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。3ヶ月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及びもし症状が残存した場合の後遺障害認定のために必要であると判断しました。相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、膝と腰がそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。
素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。
本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。
本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。
【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害認定申請により併合14級が認定
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例(60代 男性)
事故態様 自転車vsタクシー
被害者は自転車で走行中、曲がろうとした車両に巻き込まれました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。被害者には、本人は事故に遭うまで自覚していませんでしたが、頚椎に椎間板ヘルニアの兆候がありました。被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2ヶ月間の延長する協議がまとまりました。その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8ヶ月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。
こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。
本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。
自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。
後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号認定。160万円の支払いを受けて解決
「異議申立」に関する解決事例
事例の概要
後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決 (40代 男性 自営業)
事故態様 バイクvs車
被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 12級13号
解決に至るまで
被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
コメント
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。
本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。また機器の精度によっても診断能が変化します。たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。
本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。
非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により12級が認定され、1100万円増額
事例の概要
異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvs車
被害者がバイクで直進していたところ、左折車両に跳ねられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。
本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。
【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により14級認定。290万円の支払いで解決
事例の概要
異議申立により12級の認定を受け、630万円の支払いで解決(50代 会社員)
事故態様 車vs車
被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた車にぶつけられました。
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害14級が認定されました。この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。
後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。
後遺障害等級認定を受けた方、是非一度当事務所までご相談ください。
【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級獲得。630万円の支払いで解決
事例の概要
非該当から異議申立てにより後遺障害併合6級が認定(60代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は自動車で走行中、交差点で相手方車両と出会い頭に衝突しました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故により、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しましたが、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。
解決のポイント
高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。
本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。
被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。
交通事故の賠償は弁護士で変わります。
後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。
【高次脳機能障害】非該当から異議申立てにより併合6級の認定を受けた事例
事例の概要
後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例(40代 男性)
事故態様 車vs車
被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。
解決に至るまで
被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。むちうちときくと、軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。
頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。
本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。
頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」という所に送られ審査されます。調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです。そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります。
後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。実に2倍以上の差があります。
本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。
後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。
当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害等級12級が認定され、680万円の支払いを受けて解決
非該当から異議申立を行い、併合第14級が認定された事例(30代 女性 会社員)
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は駐車するため停止していたところ、被害者の車両を確認せずバックしてきた相手方車両と衝突し負傷しました。
認定された後遺障害等級
併合14級
神経系統の機能障害 14級9号(頚椎・腰椎)
解決に至るまで
この事故で被害者は、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。
後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申し立てを行い、自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合第14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。
解決のポイント
被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。
本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上異議申立を行ったところ、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合第14級の等級認定を得ることができました。
自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。医師は医療の専門化ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】非該当から異議申立により後遺障害併合14級認定
「過失割合」に関する解決事例
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例(40代 女性)
事故態様 車vs車
被害者は、車で走行中、右折のために一時停止したところを後ろから相手方車両に追突されました。
認定された後遺障害等級
神経系統の機能障害 14級9号
解決に至るまで
被害者はこの事故により、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためにポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
本件で争点となった問題に「過失割合」の点がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、過失割合と責任割合、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められたかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先行で物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は、事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、なかなか容易に覆せないことが少なくありません。
本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。
物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースで、傷害部分の賠償額の過失1割分は大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。
【頚椎捻挫】後遺障害14級が認められ、270万円の支払いを受けて解決
「異時共同不法行為」に関する解決事例
後遺障害等級14級。総額700万円の賠償金を得ることが出来きた事例(50代 男性)
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は交差点において赤信号のため停車していたところ、後方からきた自動車に追突されるという事故に遭いました(第一事故)。ところが、第一事故で負った怪我の治療をしていた被害者は、第一事故から数ヶ月後、交差点において赤信号のため停車していたところ、後方からきた自動車に再び追突され受傷しました(第二事故)。
認定された後遺障害等級
14級相当
局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この二度による交通事故により、頚部挫傷、腰部挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部、両肩、両上肢、腰部及び右大腿に痛みや痺れが後遺症として残ってしまいました。
保険会社より、治療の打ち切り、後遺障害等級認定申請の話が出ていた被害者は、後遺障害の申請はしたいが、短期間に二度交通事故に遭っていることから、どの相手方の保険会社に、どのように申請をしたらよいのか、また、被害請求について、どの相手方の保険会社に、どのように請求をしたらよいのか分からないため当事務所までご相談にみえました。
ご依頼を受けた後、当事務所の弁護士は、本件事故2つの事故が異時共同不法行為に該当するため、異時共同不法行為の特性を踏まえた上で、第一・第二事故の保険会社と示談交渉を行いました。結果、第一事故と第二事故あわせて700万円の賠償金の支払いを受けて解決に至りました。
コメント
交通事故に遭ってしまった被害者のなかには、時に、前の事故の治療中に、二度目の事故に遭い、同じ部位を怪我してしまうことがあります。これを「異時共同不法行為」といい、異時共同不法行為は賠償問題が複雑なため注意が必要です。とはいえ、複数の交通事故に遭い、怪我で心身ともに耐え難い状況に置かれている被害者にとって、複雑な賠償問題を自身で解決することはとても負担が大きいです。したがって、複数の事故に遭ってしまった場合は、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
<異時共同不法行為とは>
「異時共同不法行為」の何が難しいのかというと、それは被害者に最終的に生じた損害について、双方の事故の加害者がどこまで賠償責任を負うのかという責任の分担がはっきりしないという点です。
裁判上では、二つの考え方があります。
一つ目は、異時共同不法行為が、①民法719条1項の「共同不法行為」にあたる、という考え方、二つ目は、②「不法行為の競合にすぎない」とする考え方です。①と②では、損害賠償を求める相手やその求めることができる範囲が異なります。
①の場合は、第一事故、第二事故の加害者双方に生じた損害の全額請求することも、どちらか一方に全額請求することもできますが、②の場合は、それぞれの事故が被害者に与えた被害の影響の寄与度に応じて加害者に賠償請求する必要があります。寄与度は被害者側で証明をする必要があります。したがって、②の方が被害者にかかる負担は大きくなるといえます。しかし、近年の裁判所の見解では、この「不法行為の競合にすぎない」との考え方が主流となっています。
したがって、正当な賠償を受けるためには、両者とどう交渉していくかが重要なポイントとなります。
<気をつけないといけないのは示談のとき>
第一事故の治療中に第二事故が発生した場合、治療費の立替は第一事故の相手方保険会社から、第二事故の相手方保険会社に引き継がれることが多いです。
そして、多くの場合、第一事故の保険会社はこのタイミングで示談をすすめてきます。被害者としては、まだ治療は継続しているのに示談をしていいのか、その判断は難しいと思います。ここで注意しなければならないのは、第二事故の保険会社が治療費の支払を引き受けたからといって、全ての賠償責任を第二事故の保険会社が引き受けたのではない、ということです。
そもそもなぜ第二事故が発生した段階で、第二事故の保険会社が被害者の治療費対応を引き取ることが多いのかというと、それは二つの事故の境目を基準として、第二事故の保険会社が治療費の支払を負担したほうが、その後の処理がわかりやすい、というあくまで保険会社側の事情によるものだからです。
したがって、ここで不用意に示談してしまうと、後々にトラブルに発展してしまう可能性があります。
たとえば、第二事故がとても軽微だった場合は、第一事故の相手方保険会社と示談した後に治療を終了し、第二事故の保険会社と最終的な示談をしたいと思っても、第二事故の保険会社から「責任の大半は第一事故の保険会社にある」と賠償について争われ、場合によっては一部賠償を受けられないといった事態が生じることになります。
このように、第一事故の加害者と示談をするか否か、第一事故、第二事故における寄与度の判断、第一事故、第二事故の加害者との交渉など、異共同不法行為にあたるケースは複雑です。
本件の場合、当事務所の弁護士は、異時共同不法行為という特性から、第一事故によって生じた損害については、第一事故保険会社に請求し、第二事故によって生じた損害については、第二事故保険会社に請求し、後遺障害に基づく損害については、第一事故保険会社、第二事故保険会社双方に請求しました。そして、これまで異時共同不法行為の事案に携わってきた経験をもとに第一事故の保険会社、第二事故の保険会社と交渉を行い、総額約700万円の賠償金を得ることが出来ました。
もし、不幸にも短期間に二度の交通事故に遭ってしまった場合には、異時共同不法行為の特性、加害者が負う寄与度を理解し、交渉できる経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。
【頚部挫傷 等】後遺障害等級14級二度の事故に遭い、総額700万円の支払いで解決した事例
「逸失利益」に関する解決事例
事例の概要
当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級13級の認定を受け、550万円の賠償で解決
(30代 女性 会社員)
事故態様
バイクvs車
解決に至るまで
この事故により被害者は歯牙欠損の怪我を負いました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。
歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。
これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。
この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。
【歯牙欠損障害】13級の後遺障害で550万円の賠償を受けた事例
事例の概要
事故態様 車vs車
被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。
認定された後遺障害等級
14級9号 局部に神経症状を残すもの
解決に至るまで
本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。
コメント
交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。
その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。
●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。
●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。
逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。
本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。
後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。
【頚椎捻挫】後遺障害14級 相手方保険会社提示の金額から185万円増額して解決
事例の概要
後遺障害認定申請により併合8級が認定された事例(20代 男性)
事故態様 同乗者
被害者は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。
認定された後遺障害等級
併合8級
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
コメント
本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。
「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。
複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。
本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。
裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。
また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。
逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。
【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により併合8級が認定
事例の概要
後遺障害認定申請により12級相当が認定された事例(40代 女性)
<事故態様>
自転車vs車
被害者は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの
解決に至るまで
被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。
コメント
嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。
交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。
嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。
嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。
交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。
生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。
【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により12級相当獲得
事例の概要
後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例(60代 男性 会社員)
事故態様 バイクvsトラック
被害者は、停止中に信号無視をした車にはねられました。
解決に至るまで
被害者は、この事故により右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1ヶ月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。
解決のポイント
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。
逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。
労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。
賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。
また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。
【TFCC損傷】後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得
事例の概要
併合11級の認定を受けた事例(10代 男性 学生)
事故態様 歩行者vs車
事故当時、被害者はまだ小学生でした。
公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところをトラックに跳ねられました。
解決に至るまで
この事故で被害者は足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で併合11級の認定を受けた後、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。
解決のポイント
この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。
<過失割合>
依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。
過失割合が6:4から8:2になったことによって、賠償額が550万円増額しました。
<逸失利益>
相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。
この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。
当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。
【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】併合11級の認定を受けた事例
事例の概要
後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例(70代 女性)
事故態様 自転車vs車
被害者は横断歩道を横断中、相手方車両に跳ねられました。
認定された後遺障害等級
8級相当
せき柱に中程度の変形を残すもの
解決に至るまで
被害者は、この交通事故により胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。
当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。
解決のポイント
本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。
骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。
交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。
まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。
最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。
二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。
圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。
申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。
三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。
つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。
もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。
例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。
本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。
当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。
【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例
事例の概要
変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例(30代 男性)
事故態様 車vs車
相手車方車両との正面衝突。
認定された後遺障害等級
併合8級
脊柱の変形障害 8級相当(胸椎)
局部に神経症状を残すもの 14級9号(頚椎・胸部)
解決に至るまで
被害者はこの事故により胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。
解決のポイント
後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。
また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。
労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。
本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。
交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。
【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害8級相当の認定をうけた事例
「加重障害」に関する解決事例
「将来の介護費用」に関する解決事例
「時効」に関する解決事例
ご依頼者からの声
当事務所では、ご依頼者の方から頂いたアンケートを元に日々サービスの向上に努めています。ご依頼いただいた方のメッセージの一部をご紹介します。(ご本人の了承を得たうえで掲載しております。)
後遺障害等級
認定申請
交通事故により怪我を負ってしまった場合、それを完全に治すのが一番の目標です。しかし、長期に亘って治療を継続したにも関わらず、怪我の症状が残ってしまうことがあります。このような場合は、自賠責保険へ後遺障害認定申請をし、等級の認定を受けることになります。適切な等級の認定を受けるためには、事故初期から被害状況等の証拠を収集し、治療期間は適切な治療や検査を受けつつ、そのことを継続して記録に残しておくことが求められます。当事務所では、 適切な後遺障害等級の獲得に向けて治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までの一貫したサポートを行っています。
料金ご案内
交通事故の法律相談料は無料です。
通常料金
- 着手金
- 無料
- 報酬金
- 220,000円+回収額の11%
※加入している自動車任意保険に「弁護士費用特約」がついている方は、相談費用10万円、弁護士費用300万円までを特約で賄うことができます。
弁護士費用特約を
ご利用の場合
加入している自動車任意保険に「弁護士費用特約」がついている方は、相談費用10万円、弁護士費用300万円までを特約で賄うことができます。
- 着手金
-
125万円以下の場合
110,000円
300万円以下の場合
回収見込み額の8.8%
3000万円以下の場合
回収見込み額の5.5% + 99,000円
3億円以下の場合
回収見込み額の3.3% + 759,000円
3億円を超える場合
回収見込み額の2.2% + 4,059,000円
- 報酬金
-
125万円以下の場合
220,000円
300万円以下の場合
回収額の17.6%
3000万円以下の場合
回収額の11% + 198,000円
3億円以下の場合
回収額の6.6% + 1,518,000円
3億円を超える場合
回収額の4.4% + 8,118,000円
- 時間割報酬
- 22,000円 / 1時間
※より詳しく知りたい方は弁護士費用のページをご覧ください。